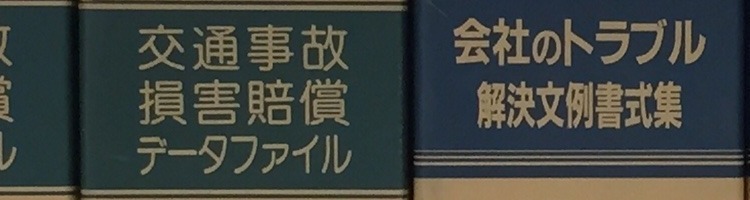- ホーム
- 会長武藤のマンスリーブログ
会長武藤のマンスリーブログ
2020年10月
猛暑だった夏も終わり、最近は朝晩が肌寒くなりようやく秋の到来となりました。
これからは行楽シーズンと言いたいところですが、まだまだ新型コロナウイルスの心配もあり、旅行を控えられている方も多いのではないでしょうか。
出かけるとしても公共交通機関ではなくマイカーで、と言う方もおられるかと思います。
今回は自動車保険にセットされているロードサービスについてお話します。
従来ロードサービスと言えばJAFが主流でしたが、最近は自動車保険に無料で付帯されたロードサービスを利用される方が多くなっています。
これは各保険会社がサービス運営会社と契約しており、ご契約者様が利用できるものとなっています。
JAFの会員ですと牽引距離15kmまでが無料ですが、保険会社のロードサービスの場合、牽引費用で15万円分(普通自動車なら180km程度)等、保険会社によって異なりますが、概ねJAFより無料範囲が長いと思われます。
提携している車屋さんが共通していることも多いので、JAFを呼んでも保険会社のロードサービスでも同じ業者さん、ということも多々あります。
牽引だけでなく、バッテリー上がりやパンクなどの応急処置も行ってくれますし、「サービス」なので翌年以降の保険料にも影響ありません。
特約にもよりますが、帰宅するため交通機関を利用した場合の費用や宿泊代、現地で修理が完了した車の回送費を支払ってくれる場合もありますので、ご自身の保険に付帯されているサービス範囲を確認される事をお勧めします。
注意点としては、ぬかるみや積雪でのスタックはサービス対象外になり、有料になる場合もあるかもしれませんのでご注意ください(JAF会員の場合は無料です)。
ロードサービスの要請は車のナンバーとご契約者名ぐらいで保険証券がお手元になくても大丈夫ですが、フリーダイヤルは携帯電話に登録しておく事をお勧めします。
一旦、自宅に持ち帰って、翌日以降に修理工場さんへ持って行ってもらう事も可能です。
損保ジャパン社のロードサービスの詳細はこちらをご覧ください↓↓↓
https://www.sompo-japan.co.jp/kinsurance/automobile/thekuruma/sche/road/
(くすのき瓦版10月号寄稿記事を再編集しています)
2020年9月
今回も前月号に続き自動車事故の示談について取り上げたいと思います。
皆さんが加入されている自動車保険は大抵が示談交渉付きになっていて、事故の際の煩わしい交渉は保険会社がおこなってくれるものと考えられていると思います。
しかしながら、こちらが全面的な被害者になった時に代理店や保険会社に連絡したところ「お客様に過失がないのであれば当社は示談の窓口になれません」と言われた事はありませんか?
ただでさえ不安な事故の示談交渉なのに力になってくれない、相手保険会社に丸め込まれたらどうしようなどと、その対応に不満をもたれる方も多いのではないでしょうか。
そもそも示談交渉は当事者本人か正当な委任を受けた弁護士など資格を有するものに限られています。
しかしながら、毎日数多く起こる交通事故の早期な示談解決を鑑み、事故当事者に成り代わり保険金を支払う立場の保険会社が示談交渉を行うことは容認されています。
しかし相手に対してこちらの過失がないため保険金を支払う当事者にならない場合は示談交渉に介入する事ができないのです。
とは言え、相手保険会社が認めれば専門的な知識がないお客様に代わり示談交渉のお手伝いをする事もない訳ではありません。
もちろん報酬をいただく事もありませんし、うまく説明できないお客様の実情を代弁したり、相手保険会社の言い分を解説する等できる限りのお手伝いをするのですが、それでも示談交渉が進まない場合は弁護士特約を付けていただいて
いる場合は弁護士への委任も視野に入れることになります。
(くすのき瓦版9月号寄稿記事を再編集しています)
2020年8月
お盆も過ぎましたが、まだまだ猛暑日が続いております。皆さまいかがお過ごしでしょうか?
さて、先月号までトラブルになりやすい自動車事故の例を紹介しておりましたが、今回は示談交渉においての困った一例を取り上げます。
こちらが直線道路を走行中、相手車がコンビニなど店舗駐車場から出てきて衝突に至った場合、もちろん路外から本線に出る場合相当の注意義務が生じますので基本の過失割合は相手車9割こちらが1割となります。
しかし仮に相手車が高級外車で修理額が70万円(最近は衝突安全センサーなどが付いたりして部品代が高額になる傾向があり決して大げさではありません)対して、こちらが10年以上経った軽自動車で修理代が30万円だったとしましょう。
この場合、こちらから相手には70万円の内、こちらの過失1割分で7万円の支払義務が生じます。
反対に相手からはというと、こちらの修理代30万円の9割で27万円の支払義務があるかというとそうではなく、こちらの車両の時価(この場合だと15万円位でしょう)の9割の13万5千円が基本となります。
となると過失はたった1割なのにもらえる保険金は修理代の半分にも満たず、しかも相手に7万円払わなければならず保険を使わなければ差し引き6万5千円しか手元に残らずでは多くの方は納得できないのは無理もないでしょう。
しかも保険を使えば翌年度以降の保険料も上がります。
とは言え、上手く交渉すれば実際の流通価値を考慮して時価額を上げてもらうこともありますし、最近はそういった場合のために修理するのであれば時価額プラス50万まで修理を認める特約が付帯されていることが多いので、対応できるケースも多いのですが、これは相手当事者が特約使用を承諾する必要があり、義務ではありません。
あくまでも時価額を超える賠償は必要ないという民事の基本原則が優先します。
ですので、こういったケースに遭った場合は、自身がご加入の保険会社や取扱代理店と相談を重ねて慎重に対処してください。
(くすのき瓦版8月号寄稿記事を再編集しています)
2020年7月
梅雨の真っ最中で鬱陶しい天気が続きます。
この時期は弊社のある京都四条通りは祇園祭の鉾立てが始まり、祭りの雰囲気を醸し出している頃なのですが、御承知の通り今年は祇園祭の鉾立てが中止となりひっそりとしていて非常に残念です。
いつもなら交通規制で道も大変混雑して、内心迷惑だと感じていた事もありましたが、いざ無くなるとなるとやはり寂しいものですね。
さて今回は前月に続きトラブルになりやすい自動車事故の例を紹介します。
皆さんはゼブラゾーンというのをご存知でしょうか。
幹線道路などでよく右折レーンの手前などにある格子模様のスペースですが、その模様がシマウマみたいなところからそう呼ばれていますが正式には導流帯と言います。
車両の安全かつ円滑な走行を誘導するため設けられています。
走行してはならないと思っている方も多いかもしれませんが、実は道路交通法上では規定が無く、走行しても違反には問われません。
しかしながら他の車からすると、まさかそこを走行してくると思わない事もあり、いざ事故が生じた場合には、ゼブラゾーン走行車両には10〜20%の過失が加えられます。
仮に本線を走行していたA車が右折のために車線変更をして後続のB車と衝突した場合、A車70%対B車30% の過失割合が、B車がゼブラゾーンを走行していた場合は50%対50%になる事もあります。
ですからいくら本線が混んでいて一気に右折レーンまでと慌ててゼブラゾーンを突っ切るような事はせず、違反ではなくとも周りの交通に十分配慮した運転を心掛けましょう。
(くすのき瓦版7月号寄稿記事を再編集しています)
2020年6月
最近、特に関西では新型コロナウイルスの感染が落ち着いてきましたが皆さまいかがお過ごしでしょうか。
暑くなってきてマスクをしなければいけないのがつらくなってきました。
マスク着用による熱中症の増加も懸念されています。皆さまどうぞお気をつけください。
さて、今回は少し新型コロナウイルスの話題から離れて意外と揉める自動車事故について取り上げたいと思います。
おなじみのコンビニエンスストア。便利なので多くの方が利用されていると思いますが、その分駐車場内での事故は多いのです。
特に出ようとする車と、停めようとする車との事故が多く、相手がバックしてきたので自分は停まっていた。または周囲の安全を確認して慎重に走行していたのに、駐車スペースから突然相手が出てきた。
それなのに保険会社同士の示談では過失を求められ、納得がいかないという事例が多く見られます。
その理由として駐車場内での事故は、一般道路ではないため過失割合の基本が50対50が支持されている事、事故の状況がなかなか証明できない事、現場では一定の相互理解があっても後日になるとそのあたりが怪しくなってくる事が挙げられます。
最近では弁護士特約を付帯されている方も多く、納得いかない方は裁判まで持ち込まれます。
しかしながら裁判所においても駐車場での物損事故(民事)は双方の注意が足りていないとの基本概念があり、勝訴するのは困難を極めます。
裁判所に持ち込めば相手保険会社の理不尽な過失割合提示は証言や物的証拠を精査し適切な判断が得られると信じ訴えを起こされるのですが、後で揉めないように現場で双方が事故の状況をしっかり合意できれば越した事はありません。
ドライブレコーダーがあるのも有益でしょうし、可能かどうかわかりませんが防犯カメラを見せてもらうなどの証拠が重要になるでしょう。
(くすのき瓦版6月号寄稿記事を再編集しています)
2020年5月
まだまだ終息とは程遠い新型コロナウイルスですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
弊社では全て在宅勤務という訳にもいかず、事務社員は時短勤務にし、営業社員はお客様に確認の上、対面での面談を控え電話や郵送にての対応を基本としています。
保険会社は80パーセントが在宅勤務としており、かなり不便な状況ではありますが出来るだけお客様にご迷惑をお掛けしないよう取り組んでおります。
まだまだ予断は許しませんが、幸い弊社の関係者、お客様からの新型コロナウイルスの感染はありません。
保険と新型コロナウイルス関してですが、生命保険では感染による入院もしくは医師によりホテルや自宅療養を指示された場合は入院給付金をお支払いいたします。
しかし、感染された後に新たな生命保険にご加入いただく場合は各社バラツキがありますが、引き受け不可となる事が多いようです。
損害保険で多く問い合わせ頂いたのが緊急事態宣言を受けての休業による利益補償についてでしたが、お支払い対象外でありお応えする事ができません。
私どもの仕事は非日常を日常に戻す仕事だと教わりました。
今まで事故や自然災害などの場合は常にその言葉を念頭に対応を心掛けておりましたが、今回ばかりはどうする事も出来ず無力感すら感じます。
お客様の中には、廃業される方も出てきました。この数ヶ月のダメージだけでなく今後の見通しが立たないとの事で決断されました。
それぞれのお客様、従業員の事を考えると断腸の思いであったろう事は想像に難くありません。
このままだと自粛要請が解かれた後には何も残っていなかったっていうことにもなりかねません。
このコラムも本来なら緊急事態宣言解除予定であった5月7日に寄稿しています。しかし宣言は5月末まで延長となってしまいました。
皮肉にも快晴の日が多く、逆に辛くなります。
明けない夜は無い、夜明け前が一番暗いと言います。
その言葉を信じて。1日も早く日常に戻りますように。
(くすのき瓦版5月号寄稿記事を再編集しています)
2020年4月
前号の投稿から約1か月が経ちましたが、新型コロナウイルスの拡がりは衰えを見せず、世界的にも感染者が増大しています。
発祥の中国を上回り、スペイン、イタリアでは既に一万人以上が死亡し、各国で外出規制が行われ医療崩壊の恐れだけでなく経済への影響も相当深刻な状況となっています。
人類は過去にも目に見えない敵である多くの感染症と闘ってきました。
まずはペスト、黒死病とも呼ばれ過去に3度ほど大流行し、14世紀の流行では当時の世界人口4億5千万人の約20%が死亡しました。
スペイン風邪、1918年に大流行し当時の世界人口20億人のこれまた約20%程が感染し、3千万から5千万、一説には1億人が死亡したとされる過去最大の感染症でした。
他にも結核や天然痘、コレラ、SARS、MERSと挙げればきりが無いほど人類の歴史はウイルスや菌との闘いの歴史であり、過去に何度も危機を迎えた事が判ります。
今回の新型コロナウイルスがそこまでの感染力、致死率を持つのか、それまでにワクチンなどの開発も含めて人類が勝利を収めるのかとても重要な段階に入ってきました。
国際的に人や物が動くことで成立している現代社会ではこの状況が続くことは国家単位で破綻を招きますし、違った問題があちこちで巻き起こることは容易に想像できます。
政府による緊急事態宣言が発令され、早や3週間となりますが、未だ各地で局地的に拡がるいわゆるクラスター感染や、感染経路不明な感染者が増大している状況が続いています。
今後の生活はどうなるのか、果たしてこの難局に国民が一丸となって耐えうるかのか…来月には、何とか収束の兆しが見えてきましたと書きたいところです。
どうぞ皆さま方も最大限の感染予防にお努めください。
(くすのき瓦版4月号寄稿記事を再編集しています)
2020年3月
先月はがんの早期発見方法として一滴の尿から線虫を利用する検査を紹介しました。
そして今回は、先日見学させていただいた京都府立医大病院の陽子線療法を紹介しようと思っておりました。
しかしながら、巷ではやはり新型コロナウイルスの話題で持ちきりです。
今や国民病とも言えるがんも怖いですし、この季節やはり思い出すのは東日本大震災に代表される自然災害などから我が身を守るには…と考えてまいりましたが、
「ウイルス感染」という目に見えず防ぐ手立てが見つからない等、侮れない脅威である事を痛感させられました。
しかもその感染範囲は世界中に広がり、経済界にも大打撃を与えております。
未だに発生の詳細も分からず、一説によると変異を経て2種類のウイルスが見つかったとか、生物化学兵器ではないかとの憶測も広がり、
感染者の実態数も定かでない状況では、終息の兆しが見えない中、皆様の不安も相当なものでしょう。
小職の家内はドラッグストアに勤めておりますが、パニックに陥ったお客さんがルール無視で我先にマスク、トイレットペーパー、消毒液を買い占める姿を見て、
人の見たくない部分を多く見たと嘆いておりました。
日本人は苦難においても助け合い、節度ある態度のある国民だと言われておりましたが、そうでも無い方がいるというのも事実です。
現状では多くの施設の閉鎖やイベントの中止がいつまで続くかわかりません。
小職の事務所のある京都四条もホテルはガラガラ、観光客も激減しています。
このような状況でも対応できる損害保険も少なく、企業経営においては相当深刻な状態です。
早く終息方向に向かうか、有効なワクチンが開発される事を期待しながら見守ることにしましょう。
(くすのき瓦版3月号寄稿記事を再編集しています)
2020年2月
巷ではコロナウイルスの蔓延で感染者の拡大が心配されています。京都でも何人かの患者が見つかり今後が心配ですが、まずは手洗い、うがいを心がけ体調管理していきましょう。
さて、今回は今や国民病とも言えるガンについて取り上げたいと思います。
以前は不治の病とされたガンも医療技術の進歩により随分と治癒率は高くなってきました。
しかし最も大切なのは早期発見、早期治療です。
今回は早期発見の新しい方法として線虫ガン検査についてご紹介します。
これは九州大学初のベンチャー企業、「HIROTHUバイオサイエンス」が開発した検査方法で体長1ミリの線虫を使い尿一滴でガンの有無を80%以上の確率で発見できるとして
今年から9800円という安価な費用で実用化されたものです。
線虫は土壌などに生息する微小生物。犬より優れた嗅覚でガン患者の尿に含まれる特有の臭いに近づき、健康な人の尿からは逃げる性質を利用します。
ガン患者1400人に実施した検査では的中率は約85%に上り、特にステージ0〜1では87%まで判定でき一般的な検査方法の腫瘍マーカーよりもかなり高確率です。
反応するのは胃、大腸、肺、膵臓、肝臓、子宮、前立腺など15種類のガン。
現時点ではガンの部位までは判明しないが今後は特定も目指しているとのこと。
尿を同社の検査機関に持ち込み解析、結果報告までは1週間から1ヶ月(取り扱い施設を通じて)。
1年目は25万人の解析が可能で既に問い合わせが相次ぎ既に約10万人の検査が予定されています。
同社は当時、九州大学助教授だった広津崇亮社長が設立。福岡県と久留米市の支援を受け開発を進めました。
広津社長は「技術的な検証はほぼ終わった。ガンの検診率を上げるには画期的な技術が必要。特に子育てや仕事で検診率の低い女性の検診率アップにつなげたい」と話しています。
現在、取り扱い施設(病院等)は限られていますが、このような簡易かつ高精度な検査がどこでも受けられるようになってほしいものです。
(くすのき瓦版2月号寄稿記事を再編集しています)
2020年1月
あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。
皆様におかれましてはどんなお正月を過ごされましたか?この記事は弊社の仕事始めの1月6日に書いております。
当初心配されていた年末年始のお天気も比較的穏やかで、関西の各地でも初日の出が拝め、全国的にも大きな事故、事件もなく静かなスタートとなったのではないでしょうか。
弊社でもお客様からの緊急の場合として固定電話を転送設定し対応しておりましたが、幸いにも1件の電話もなく安心しているところです。
とは言え、過去の被災地の方々にとっては完全な復興はほど遠く、不便なお正月を過ごされた方も多いのではないでしょうか。
今年は東京オリンピックが開催されます。
小職が生まれた昭和38年の翌年に前回の東京オリンピックが開催されてから56年。
当時は高度成長時代でどんどん近代化が進み便利になりました。
しかしながら災害に強い街づくりができていたかは果たしてどうだったでしょうか。
今回は復興五輪という位置付けでもあるのですから、猛威を振るう自然災害にも耐えうる街づくりに真剣に取り組んでもらいたいところです。
併せて国内外から多くの人々が訪れます。テロを含めた人災の防止に努めて安心、安全な日本であって欲しいと思います。
来月以降、今年もこのコラムを通じて皆様に色々な情報を提供してまいりますので、是非ともご拝読お願い申し上げます。
次回はがんの早期発見として注目を浴びている「線虫検査」について紹介したいと思います。
(くすのき瓦版1月号寄稿記事を再編集しています)
-
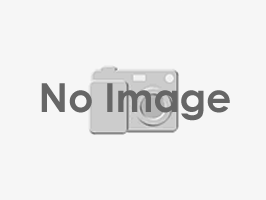 6月18日(水)
こんにちは。営業の小森です。来年4月1日から自転車の交通違反に対して「青切符」による取り締まりが導入されること
6月18日(水)
こんにちは。営業の小森です。来年4月1日から自転車の交通違反に対して「青切符」による取り締まりが導入されること
-
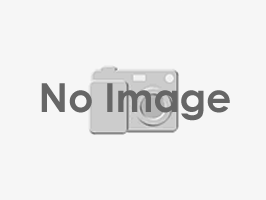 6月25日(水)
皆さまこんにちは。営業の城石です。数日前に梅雨入りしてから雨が降ったり止んだり、スコールのような強い雨が降った
6月25日(水)
皆さまこんにちは。営業の城石です。数日前に梅雨入りしてから雨が降ったり止んだり、スコールのような強い雨が降った
-
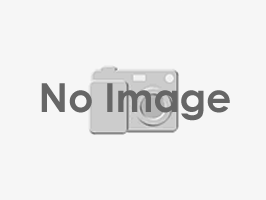 7月2日(水)
こんにちは営業 三宅です【夏の風物詩】下鴨神社「みたらし祭」で心身清めるひととき京都・下鴨神社で毎年土用の丑の
7月2日(水)
こんにちは営業 三宅です【夏の風物詩】下鴨神社「みたらし祭」で心身清めるひととき京都・下鴨神社で毎年土用の丑の
-
 7月23日(水)
こんにちは。 夏が本格的になり、体調も崩しやすい時期ですが皆様いかがお過ごしでしょうか。私は、絶賛夏バテ中で朝
7月23日(水)
こんにちは。 夏が本格的になり、体調も崩しやすい時期ですが皆様いかがお過ごしでしょうか。私は、絶賛夏バテ中で朝
-
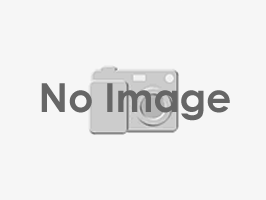 7月30日(水)
こんにちは営業の大村です。毎日、暑い日が続きますが皆様いかがお過ごしでしょうか。本日は、予想最高気温が40℃、
7月30日(水)
こんにちは営業の大村です。毎日、暑い日が続きますが皆様いかがお過ごしでしょうか。本日は、予想最高気温が40℃、